
昨日のブログ「adizero Feather RK2」が早くも壊れたんですけど〜!」に対して下記のような返信をtwitterでもらいました。もしかしたらわたしは裸足ランナーとしてものすごく深いところにぶつかったのかもしれません。
@tshige07 私は裸足ラン、裸足感覚ランをやって下駄で走れる様になったので、このままやっていけばどの靴でも走れる足になっていくのだと思い込んでいました。靴も高機能にするのと同時に走りの種類が狭まってしまったのでしょうか
— 藤原祐太@万博たこやきマラソン (@yuta_warao0806) 2016, 1月 22
twitterの返信にあるようにわたしも裸足を追求していくことでどんなシューズでも走りこなせると思っていました。でも「走りの種類が狭まってしまったのでしょうか」という言葉が妙にわたしの中に残ります。
スポンサーリンク
裸足が万能じゃないのは理解していますが、裸足での走りをベースにシューズを履くという発想はもしかしたら正しくないのかもしれません。裸足ランナーがシューズを履くというのは、シューズの上にさらにシューズを履くような行為だとしたら?
そんなことはないという思いと、もしかしたらその可能性は否定出来ないという思いが頭の中で交錯します。
わたしが理想としている足は、柔軟性がありどんなシューズでもフィットさせることができる、どんな路面でも最適な走りのできる適応力のある足です。いまの裸足ランニングを追い求め方がこの理想に逆行しているのではないかという気持ちが消えません。
もちろん裸足ランニングをやめるとかそういう話ではなく、もはや「裸足=楽しい」というだけでは心も体も裸足ランニングに対して納得しない段階に来てしまった気がします。
裸足で走ることの研究は様々な人がやっていますし、個人でもそれぞれが経験値を高めています。難しいことはそういう人たちに任せてわたしは感覚を大切に…なんて思ってましたが、もう少し真面目に裸足と向き合う必要がありそうです。
裸足で走ることが一つの方向性にだけ特化したものにならないためにどうすればいいのか。
ものすごく大きなテーマですが、わたしがこれから何十年も時間をかけて向き合うテーマのひとつになりそうです。適応力の高い足を裸足ランニングで作るにはこれまでと同じ方法ではダメだということははっきりしました。
昔から転んでもただでは起きないタイプなわたしはシューズを壊してもただ嘆くだけで終わらせるわけにはいきません。ひとつの大きな気付きとなって河童式ランニング法の原点にしていきます。
もしかしたらわたしがずっと追い求めている「近代以前の日本人の走り」につながる何かをつかめそうな気もします。
そのときは「伝説のシューズ破壊事件」として将来100万部発行の自叙伝に掲載するとしましょう。
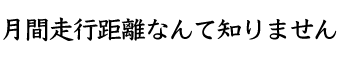








コメント