
今年の福岡国際マラソンは、久しぶりに開催前から活気のある大会でした。海外からの招待選手としてウガンダのキプロティク選手や、昨年優勝したエチオピアのイエマネ・ツェガエ選手といった華のある選手はもちろんのこと、日本人でも期待の若手が揃った大会でした。
東京オリンピックでのマラソンに出場するには、今回は1つの選考レースに勝たなくてはいけません。その選考レースに出るためには、この福岡国際マラソンのようなメジャーな大会で一定の成績を残す必要があります。
東京オリンピックを目指す若手としては、ボストンマラソンで鮮烈なデビューを飾った大迫傑選手、元東洋大学のエースである設楽啓太選手、山の神こと神野大地選手など、長距離好きなら誰もが期待する選手が集まっています。
東京オリンピックには興味がないと明言している川内優輝選手も、レースに負けていいと思っているわけではなく、出るレースは当然すべて勝ちに行くつもりでいるのでしょう。

そんな見どころが期待できるレースと言いたいところですが、結局このレースを制したのはナイキでした。優勝したのはノルウェーのモーエン選手ですが、本当の勝者はナイキです。
このレースの1位から4位までの選手が履いていたのは、すべてナイキのヴェイパーフライ4%です。
ヴェイパーフライ4%は一部で「ドーピングシューズ」とまで言われているシューズで、ソールにカーボンプレートを内蔵することで、テコの原理を使って推進力を生み出します。
非公式ながら、ナイキのイベントでフルマラソンの距離を2時間25秒で走りきった、現在の科学の粋を集めて作られたランニングシューズです。

シューズについては解説で触れられることはなかったかと思いますが、このシューズでタイムを出すときの独特な走り方については、何度か触れられていました。解説ではフォアフット着地と言っていましたが、正確には少し違います。
足の前側から着地するのは同じですが、体重のかけ方や足の抜き方などに独自性があります。
走り方はどうであれ、このシューズを履くと他のシューズよりも力を使わずに推進力を生み出すことができます。これまでのシューズよりも4%も効率があがると言われていますが、今回の福岡国際マラソンはそれを証明した形になりました。
ここまではっきりと結果として出てしまうと、IAAF(国際陸上競技連盟)がどこかで規制をするのではないかと不安になるくらいの差があります。ドーピングシューズと言われるのも分からなくはないです。

ただし、このシューズはきちんとIAAFに認められたシューズであるということを無視してはいけません。国際マラソンで履くシューズは、IAAFに認められたものでなくてはいけません。
「ヴェイパーフライ4%はずるい」「道具に頼るのはどうかと思う」というような意見が出てきますが、IAAFの答えは、特別なシューズではないということです。
個人として、そういうシューズを履きたくないと言うのは好きにすればいいと思うのですが、シューズの存在そのものを否定するのは、マラソン競技そのものを否定しているようなものです。
認められたシューズなのに「あれはおかしい」と言うのは、「フルマラソンが42.195kmというのはおかしい」というくらい滑稽な話です。決められたルールの中で競い合う。そのルールに則っているなら、それは批判される理由がありません。

ただし、今回ははっきりとシューズの差が出ましたし、これからさらに大きな大会ではヴェイパーフライ4%が勝ち続けることになるでしょう。アディダスが本拠地のベルリンで勝ち続けるくらいしか、他のシューズが勝てるイメージが出来ません。ただ、その牙城が崩壊するのも時間の問題でしょう。
そうなると、IAAFもさすがに平等性を保てなくなるシューズに規制をいれるかもしれません。もちろんそうならないかもしれませんが、いまだに陸王ブームに乗って薄底シューズを売ろうとしている日本のメーカーは、あっという間にガラパゴス化します。
ただし、この魔法のようなシューズ、ヴェイパーフライ4%には弱点があるとわたしは感じています。それはレース終盤、36km以降にスピードが大きく落ちる可能性があるということです。

これは根性論などで乗り切れる問題ではなく、ヴェイパーフライ4%に合ったフォームで走り続けられる筋力が求められることによるものです。
ヴェイパーフライ4%の肝はその独特のフォームにあります。まるで機械のように同じ動きをし続けないと、スピードを保つことはできません。後半に力が落ちてしまったとき、薄底シューズのように力技でスピードをキープすることができません。
頑張ろうとすればするほどスピードが落ちていく。それがヴェイパーフライ4%です。この現象はサブ2を目指したBREAKING2.0でも見られましたし、4位に入ったカロキ選手も見られました。
3位に入った大迫選手は、必死になってフォームを維持しようとしていました。速く走りたい気持ちと、正しいフォームで走るという気持ちのせめぎあい。

わたしは今回のレースをシューズブランドの勝利と言っていますが、上位の選手の努力を否定するつもりはありません。あのフォームを身につけるために大迫選手はどれだけ練習をしたのでしょう。
嫌になるほどの基礎の繰り返し。
その結果が、3分以上の自己ベスト更新につながっています。ただ、それもヴェイパーフライ4%があってのことだとわたしは考えています。
そしてもう1つ。これはわたしの推定でしかありませんが、おそらくヴェイパーフライ4%をより効果的に使うためのポイントは体重です。

マラソンはこれまで、体重が軽ければ軽いほどタイムが出るとされていました。ときには筋肉でさえも無駄なものとして削ぎ落とすのがこれまでのマラソンでした。
ところが、優勝したモーエンは178cm、62㎏の大型選手です。
彼だけは最後まで失速することなく、むしろ後半に大きな力を残して走りきることができました。この結果だけで安易に決めつけることはできませんが、このままヴェイパーフライ4%が圧倒的な立ち位置をキープするなら、おそらくこれから大型選手の時代がやってきます。
これまでは大型選手はパワーがあるもののロスも多く、なかなか勝てない時代でした。ところが、ヴェイパーフライ4%の推進力はこれまでのような軽さよりも、パワーが物を言います。多少体重が重くてもパワーがあれば、あとはシューズがカバーしてくれます。

そうなると有利になるのが欧米系のランナーなのではないでしょうか。アフリカ系ランナーの時代が終焉を迎えるのではないか、そんな未来も見えてきます。もちろん、「ヴェイパーフライ4%に規制がかからなければ」ということが前提ですが。
そんな時代に、日本人ランナーがどうやって世界と戦っていくのか。これまで通りの薄底シューズで負け戦に望んでいくのか、それとも勝ちにこだわってシューズを変えていくのか。
実業団ランナーがこのまま薄底シューズを選ぶとしたら、東京五輪のマラソン代表を決めるグランドチャンピオンシップにヴェイパーフライ4%を履いた市民ランナーが入ってくるかもしれません。
スポンサーリンク
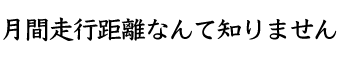

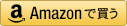








コメント