
ランニングで大事なのは肩甲骨の動きだと、最近ランニング雑誌などでとりあげられていますが、そこそこ感覚のいいランナーは肩甲骨を意識的に動かせますが、普通のランナーは正直「?」だと思います。
そういうわたしも肩甲骨を意識することはできても、肩甲骨をどうセットすればいいのかまだ探っているような状態です。
そんな中、ふと「両手を後ろで組んで走ったらどうなるだろうか?」と思ってやってみました。
最初は上体がガチガチでブレまくりで、ひどい走りだったのですが、500mぐらい走るといきなり腕の力が抜けそこそこいい感じで走れます。
ペースはゆっくりめの5分20秒/kmだったのですが、後ろで手を組んでもペースはそれほど変わらず。
これまでわたしは「6分/kmぐらいなら腕振りは不要」と言っていましたが、この感覚ならば5分/kmぐらいでも腕振りは不要な気がします。
いやそもそも腕は振るものではなく、肩甲骨の動きに連動して結果的に動くもの。
そして走りと連動した肩甲骨の動きというのが「後ろで手を組む」ことではっきりとわかるようになります。
ランニング中の体の軸とその軸に対するねじれの動き。

ただし体幹が整っていない人だと、後ろで手を組んで走ろうとすると走りがめちゃくちゃになるかもしれません。
これまで腕振りでごまかしながら走れていたのが、腕を使えないことでバランスを取りながら走れなくなる。そうなると上体が完全にグニャグニャしてヘタするとまっすぐ走ることすらできないかもしれません。
ちょっと試しに後ろで手を組んで走ってみてください。
組んだ手は力を抜いて尾てい骨の上に乗せる感じで、肩は脱力。
走るときにきちんと体の軸ができていれば腕が痛くなることもなく、リラックスした状態で走れます。
この体勢でフルマラソンを走るのはあまり現実的ではありませんが、練習の一環としてウォーミングアップやクールダウンのときに活用すると「肩甲骨の意識」が高まるような気がします。
すみません、まだ「気がする」の領域です。
そしてわたしの後傾の走りと、後ろで手を組む走りの相性がいいようで、1km走り終えた後の肩甲骨周りの筋肉のほぐれ具合が絶妙です。自然のマッサージ機です、これ。肩こりにも効くかもしれません。
ただやっぱり体幹が整ってないと難しいかな。

「後ろで手を組む」はひとつの例なのですが、じゃあ前で手を組んだらどうなる?上で組んだら?手の指を大きく開いたら?そういう「体の仕組み」を使ったランニングは、ランニングの新しい方向性を示すことができるはずです。
以前少し話したかもしれませんが「run to adjust」走ることで体が整っていく仕組み。ちょっとずつ形になってきました。
ケガの経験のないランナーさんはほとんどいないかもしれませんが、走ることがケガにつながるのは体がどこか無理をしている証拠です。
そうではなく体の仕組みを利用して、人間が本来持つ動きを取り戻す。そういうランニングがあってもいい。
それを知ってもらうにはわたしがそこそこの結果を出す必要がありますが・・・
とりあえず、後ろで手を組んで走っても何も取られませんから、1kmぐらいやってみてください。そこで何かを掴んでもらえれば面白いなと。そして自分でいろいろな動きをランニングに取り込んでみてください。
わたしも夏前までにはいくつかの動きをまた動画にして出すようにします。
スポンサーリンク
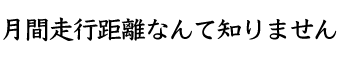








コメント