
ランニングの着地はフォアフットがいい。裸足系のランニングをしている人たちの間で、もはや常識のようになっています。そして踵着地はケガをしやすい。
すべては「BORN TO RUN」の影響ですが、「BORN TO RUN」を読んで裸足を始めた人は、どういう理屈でフォアフット着地がいいかということはあまり考えてないような気がします。
踵着地をフォアフット着地に変えたらケガしなくなった。だからフォアフット着地がいい。
間違いではないのですが、ここで問題なのは「自分のケガがなくなったから、フォアフットこそ走りの基本」としてフォアフット着地だけが正しく、踵着地そのものを否定し始めること。
本当に大事なのは踵着地の何が悪くて、どうしてケガしてしまったのかということです。
踵着地の問題は足首の角度にある

踵着地をすると着地の衝撃が、膝や股関節にダイレクトに伝わるから危険だと言われています。ではなぜ踵着地をすると、衝撃がダイレクトに伝わるのか。
これは踵着地をすると足首をロックした状態で着地してしまうことによる弊害だとわたしは考えています。
フォアフット着地の場合、着地の瞬間、足首の前側が少し伸びたような角度で接地して、そこから足首の前側を圧縮させます。
椅子に座った状態で踵を接地させて、つま先を浮かせてみてください。このときふくらはぎの前側と、足の甲の筋肉が圧縮されるのがわかるはずです。
足首の前側の角度は90度かそれ以下で、足全体の動きが限定(ロック)されているように感じませんか?
反対に足の前側を接地させて踵を上げてください。ふくらはぎと太ももの裏側が圧縮されるのを感じるはずです。そして足首の前側の動きはフリーな状態になっているはずです。
踵で着地をしたときは足首の前側の角度が狭くなって、筋肉がロックされてしまい力の逃げ場がなくなります。
これに対してフォアフットの場合は、足首がフリーの状態ですので、着地の衝撃をまず足首で受けることができ、その後、膝や股関節でも柔らかく衝撃を受けることができケガをしにくいというメカニズムになります。
フォアフットだからケガをしにくいというわけではない

じゃあやっぱりフォアフットのほうが優れていると思うかもしれませんが、大事なのはどこで着地するかではなく、足首をロックさせずに着地することです。
フォアフットでも足首がロックして走っている人は結局ケガをします。
フォアフットなら足首のロックのしようがないじゃないかと思うかもしれませんが、フォアフットというよりは裸足になったときに足首がロックしてしまうことがあります。
それが足裏に痛みを感じたときです。砂利道を走るときや、30kmくらい裸足で走って足裏がヒリヒリしてるとき、足の筋肉が緊張して足首の自由度が下がります。
フォアフットにするために裸足になったのに、裸足で走った結果、フォアフットのメリットを消してしまうことになる。
わたしも含め、裸足好きの人は「裸足だから大丈夫」と頑なに裸足で走りますが、足首がロックしてしまったら、裸足で走るのは踵着地と変わらなくらい、もしかしたら踵着地よりも危険な状態かもしれません。
またフォアフットを意識し過ぎるあまり、足首が伸びきった状態で接地する人もいます。これも足首がロックされてしまうためケガにつながります。
フォアフットの難しさは高い技術が求められることにある

さらに、フォアフットでの走りは実はかなりテクニカルな走りになります。
- 骨盤を前傾させながら足の前側で着地
- 踵を下ろしながら膝を前にスライドさせ、ふくらはぎと太ももの裏側の筋肉を圧縮
- 踵の接地をきっかけに圧縮された筋肉を開放して推進力を作る
どこがテクニカルかというと、足の前側で着地すること以外かなり難易度が高い走りになります。
その理由は足首がフリーであることにあります。足首がフリーだからケガをしにくいのですが、フリーがゆえにコントロールが難しくなります。
足の前側で着地したときに、足首をブラさないようにしながらも踵を下げ、膝をスライドさせるのですが、この動作は何度も何度も繰り返して体に覚えさせる必要があります。
もちろん正しい練習を繰り返せば身につけることができます。
わたしは裸足を始めたいという人に「裸足ランニングとかで裸足の基本をちゃんと学んだほうがいい」と言っていますが、裸足ランニングや裸足を教えている人たちは、上記の一連の動きを身につけるための練習をしているはずです。
はずだというのは、わたしは参加したことがないからわからないためですが、吉野剛さんが教えているのを見ているとそういうことだろうなということはなんとなくわかります。
じゃあなぜわたしはちゃんと裸足を習わないか。
それはわたしの裸足はフォアフット着地ではないからです。
フォアフットは難しいからフラット×後傾で走る

わたしは骨盤を後傾させて走りますが、そのときの着地はやや踵着地気味のフラットです。ランニングの常識で良くないとされていることを組み合わせています。
骨盤を後傾にすると、フォアフットでは走れません。ですので着地は「ペタッ」という感じに足裏全体で接地させます。足裏全体で接地しますが、体の前で接地させるので足首はロックしません。
正確には左右方法だけにロックをかけます。フォアフットのときにフリーだった足首の左右の動きだけ封じ込めて、力が逃げていかないようにします。
あとは上半身が接地したところよりも前側に来たところでふくらはぎとハムストリングスの筋肉を開放させます。
ものすごくシンプルです。そしてかなりのスピードを出すことができます。その代わりふくらはぎとハムストリングスの消耗がすごいことになるので、最初は1kmも走れないかもしれません。
でもそれはこれまで使っていなかった筋肉を使うからであって、体ができればなんてことなくなります。その過程で尋常じゃない筋肉痛になるためかなり焦ることになりますが。
この走り方でも筋肉さえ出来てしまえばフォアフットと同じようにケガは減ります。
わたしのフォームを見て、「マイケル・ジョンソンみたい」と表現した人がいましたが、まさにそのイメージです。胸を張るように後傾にして、地面を蹴らずにふくらはぎとハムストリングスの反発で走る。
もっとも裸足の走りも「ふくらはぎとハムストリングスの反発」で走るので、実はやってることは同じです。ただテクニカルな部分、個人的に不要だと思う動作を省いた結果が「フラット×後傾」というスタイルです。
ケガの原因は足首にある

長々と書きましたが伝えたかったのは、ケガの原因は踵着地にあるのではなく、足首の自由度が下がることによって起こるということ。そしてフォアフットでも足首をロックさせてしまうとケガをするということ。
そしてフォアフットは想像以上にテクニカルな走りを要求されるため、取り入れるにはきちんとトレーナーから走りを習うべきだということ。
わたしのように自己流というのも選択肢のひとつです。ようは足首を固めしてまわなければ、どんな走りをしていてもそう簡単にはケガはしません。それは踵着地であってもです。
踵着地からフォアフットに移行してケガが治るのは、フォアフットのほうが足首を自由にさせやすいからであって、衝撃を緩和できるというのはその結果に過ぎません。
だからフォアフットがいいと言われればそうなんですけど・・・
フォアフットがいいとか踵着地がいいとかそういう論争は、わかりやすい論争ですが、表面的なものであって本質的ではないようにわたしは感じています。
「フォアフットにしなきゃ」「踵着地にしなきゃ」と固執せずに、足首をロックさせないことだけ意識してもっと自由に走ってみると走りの幅が広がっていくはずです。
ちなみに上のハイヒールの写真は、足首が伸びきった状態でロックされた例です。ここまで極端ではありませんが、下り坂でフォアフットを意識し過ぎるとこうなりますので気をつけてください。
スポンサーリンク
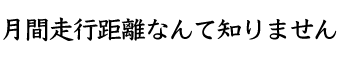








コメント