
東京には美味しいお店が無数にあって、いつも驚かされるのと同時にちょっと嫉妬する気持ちになるのですが、ときどき「どうしてこうなった?」と思うような残念なお店に出くわすことがあります。
昨日がそれで、ラン仲間と走ったあとの反省しない反省会で行ったお店。わたしが「行きたい」と強引にみんなを連れて行ったのに、入店する前から嫌な予感。お店に入るともう「ごめんなさい」状態でした。
まったく美味しくないお店ではないんですよ。お店の名誉のためにも言っておきますが。チーズや生ハムは美味しかったのですが、いろいろ残念なお店だったわけです。
何度もこのブログで言っていますが、わたしはグルメではなくただの食いしん坊です。美味しいものを食べるのが好きという、むしろ卑しいタイプの人間ですので、食に関して偉そうに言えるような味覚を持っているわけでもありません。

チェーン店が大好きですし、マクドナルドの新製品はそこそこ食べています。スキあらば吉野家に行こうとします。王将の餃子が世の中からなくなったら3ヶ月は絶望して暮らすでしょう。
チェーン店を好むのは、基本的に残念なお店に当たらないためです。感動するほどの味に会えることはあまりありませんが、大失敗もほとんどありません。安定の味と安定のサービスを受けられます。
わたしたちはあまりにあのサービスに慣れすぎて、それを「普通」を感じていますが、チェーン店でないお店に行けば、いかにハイレベルなことなのかよく分かるかと思います。

それはともかく、残念なお店のお話です。
食いしん坊も度が過ぎると、お店の入り口くらいで良いお店かどうか分かります。良く言えば嗅覚、悪く言えば……自分を貶めるのはやめておきましょう。事実だけ言えば、入り口でほぼ大丈夫な店かどうか分かります。
残念な店はいたるところに綻びが出ます。ここで言う残念なお店というのは、美味しい美味しくないではなく、トータルの満足度と考えてください。
個人的には料理の味の違いなんてそんなに分かりませんし、しょせん好みの差でしかないと思っています。一般的に受け入れられる味というのは確かにありますが。

わたしのいう残念なお店というのは「また行こう」とならないお店だと思ってもらえれば分かりやすいかもしれません。もちろんそれも好みの範囲ですが。昨日行ったお店でも、仲間の誰かは気に入ったかもしれません。
そういう意味で「あのお店良くなかった」と書くのは結構リスクがあります。「おい、俺のお気に入りのお店を残念というのはどういうことか」となる可能性が大いにあります。
なので、美味しいお店はみんなに紹介しますが、残念なお店の名前を出すことはありません。ものすごくイラッとさせられたら話は別ですが。
残念なお店は入り口に立ったときに違和感があります。整っていないというか、パーツが足りていない。いや、あるべきところにあるべきものがなかったり、あるべきでないものがあったりします。

具体的にそれが何なんなのかを説明するのは難しいのですが、見た目に統一感がなかったり、手を抜いている部分が感じられたら入店を避けます。店構えがきれいかどうかは気にしません。
これも説明しづらいのですが、統一感のある汚れというものがあります。汚れているからこそ得られる安心感があり、そういうお店を見つけたときは、かなりテンションが上がります。
反対にオシャレにしてきれいに見えても、安っぽさが表に出ていたりすると躊躇します。間違ってはいけないのは、安っぽいのがダメなのではなく、一生懸命オシャレに見せようとしているのに安っぽいのがいけません。
ファミレスなどは安っぽさを意図的に出しています。そう書くと語弊がありますので、高級感を意図的に排除していると言うべきでしょうか。安っぽくしようとしてそうなっている分には統一感があるわけです。

そういうのは店構えや、お店の前に出ているメニューなどを見れば伝わってきます。
なぜ、統一感がないお店が良くないのか。統一感がないというのは、どこかで妥協しているからです。当然それは料理の味やサービスにも出てきます。「仕方ないじゃないか」というのがいたるところに出てきます。
店員が少ないから、呼び出されてもなかなか席に行けなくて「仕方ないじゃないか」。料理の味が理想のものでなくても予算を考えたら「仕方ないじゃないか」。
わたしが好むお店には、基本的にそういう部分がありません。

「神は細部に宿る」というのは誰が言ったことか知りませんが、名言だと思います。機械設計をしていたころは、細部にこだわってモノづくりをしていました。細部を妥協すると大きなところで絶対に破綻します。
きっとそれは居酒屋やレストランなどの飲食店経営や、料理の世界でも同じだと思います。もちろんライターの世界でも同じです。細部にこだわれない人は生き残っていけません。一部の天才を除いて。
ときどき、その天才を取り上げて「あの人は大雑把でこだわったりしない」なんて言いますが、本質的に大事なところではこだわっていたりします。
大雑把だとしてもそれは天才だから許されることであり、わたしたち凡人は細部にこだわらないと、その天才たちの背中を追うこともできません。凡人であることにかけては天才的なわたしが言うのですから間違いありません。

結局抽象的すぎて残念なお店の見抜き方が分からないという人のために、最後に具体的な判断方法を教えます。
・メニューに載っている料理が写真ではなく絵
・目に入るところに材料のダンボールなどが平積み
・厨房の目に入るところに片付けた食器が並んでいる
・食べ終わったお皿やグラスが片付けられていない
・店員さんの目に力がない
・人気のお酒の空き瓶を飾っている
いろいろ書きましたが、もっと簡単に分かる方法があります。それはお店に活気があるかどうか。結局また抽象的になってしまいましたが、いいお店には活気があります。エネルギーがあります。
それは表に出ていることもあれば、内に秘められていることもあります。でもそこには確実に意思として表れます。「お客さんに喜んでもらいたい」「いいお店にしたい」という思いがあるかどうか。

これがなければ、どんなにいい材料を揃えたって、どれだけ料理の腕が良くても、トータルで残念なお店になってしまいます。
そしてそれを感じられるかどうかは、自分自身がそういう思いを持って仕事や大切な人と向き合っているかというところに関係します。普段からそういう思いを持っていない人は、きっとお店の活気やエネルギーを感じることができないような気がします。
あまり書きすぎると、まるで自分がすごい人間だって間接的に言っているような感じになるので、これ以上は書きませんが、これからお店を選ぶときに活気やエネルギーを感じられるかどうか意識してみてください。
最初は何も感じられないかもしれませんが、ある日突然それを理解できるはずです。あなたがわたしと同じ食いしん坊ならば…という条件がつきますが。
スポンサーリンク
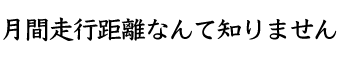

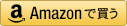








コメント