
食べ物の話ばかりが続いて申し訳ないのですが、思いついたときに書いておかないと忘れてしまう年齢になっていますので。
「粗食のすすめ」で幕内秀夫さんが、「味覚や食の好みなどは5歳くらいまでで決まる」というようなことを書いていました。読んだのがだいぶ前ですので、細かいことがあっているかどうかは分かりません。
ただ、三つ子の魂百までではありませんが、大人になってどんな食を好むかは小さいうちに決まってしまうそうです。大人になって、お腹が空いたときにマクドナルドに行くか蕎麦屋に行くかは、子どもの頃の食生活で決まると。
全面的にそれを正しいとは言いませんが、腸内細菌をベースにして考えると「なるほどな」と感じます。

腸内細菌は人それぞれ種類や数が違いますが、同じ食事をしている人はその構成が似てくるそうです。そして、腸は脳に指令を出すことができます。
これはわたしの推測ですが、現状の腸内環境を維持するために、脳に対して何を食べたいかを支持するわけです。腸が現状の腸内環境を作ったものと同じものを欲するとすれば、小さいころからの食生活をなぞろうとします。
小さいころからハンバーガーなどのファストフードを食べていれば、お腹が空いたときに腸が「ハンバーガーを食べたい気分です」と脳に伝えて、脳はそれを思考にしてハンバーガーを食べるという仕組みです。
レース後に甘いものが欲しくなったりするのも、腸からの司令と考えられます。脳が糖を欲しているのもあるのかもしれませんが、血管中の糖が足りないことに気づいた腸が脳に対して「糖を摂れ」と言うわけです。

そう考えると、すべての人に最適な健康食なんていうのはないということが分かります。
栄養面だけを考えれば最適な健康食は作れます。キムチ納豆に玉ねぎを刻んだものを食べれば腸内環境が整いますが、納豆を食べられない人や玉ねぎが嫌いな人にとっては苦痛でしかありません。
困難なものはどうやっても続きません。わたしたちはストレスに対して弱い生き物ですから。
そういう意味では、比較的健康なものを美味しく食べることができるように育ててくれた親には感謝しかありません。母は農家の育ちというのもあり「残す」ということを許してくれませんでした。

出されたものは美味しかろうが美味しくなかろうがすべていただく。
何歳くらいからそうなったのかは分かりませんが、物心がついたときにはすでに「出されたものをすべて食べる」というのが当たり前になっていました。
おもしろいもので、これは大人になってからも変わらずで、残すということに罪悪感があります。そしてちょっと足りないかなと思ったときでも、基本的にはそれ以上は食べません。
それはともかく、出されたものをすべて食べるという習慣は、好き嫌いをほとんどなくしてくれました。小さなころに食べられなかったのはエビだけですが、大人になって唯一食べられないのが「エビカツ」です。

食べられないとは別に多少の好き嫌いはありますが、基本的には何でも美味しくいただけます。そして、母の料理の影響でしょうか、素材の味を活かした食べ物を好んで食べます。
それがいわゆる健康食に該当するものです。
だからわたしはグルテンフリーにも無理なく移行しましたし、腸内環境を向上するための食事も楽しみながら続けることができています。
子どもの頃は躾の厳しさに苦しみましたが、今はそれを感謝しています。あの厳しさがあったから、健康食が苦でないどころか楽しめているわけですから。

子どもが大人になってから健康でいられるかどうかは親にかかっています。
だから子どもに対して「嫌なら食べなくていいよ」と言っている親を見ると、ちょっとだけ残念な気持ちになります。叱ることはとてもエネルギーがいることですし、上手にやらなければ親子関係も壊れます。
でも、本当に子どものことを思うなら、愛を持って嫌いなものでも食べさせたほうがいいのになと。
どうしても食べられないものはあります。アレルギーだってあるかもしれません。でも小さいころに何でも食べるということを習慣化していると、大人になったときに何かと有利です。

様々な食材を取り込むことで腸内には多様な細菌が住み着くことになり、強い内臓を作ることもできます。何よりも、健康食にしようとしたときに、抵抗なく始められます。
逆に好き嫌いで食べ物を選んでいた人は、健康食を続けるのは難しいかと思います。ストレスのほうが大きくなりますので、健康食を食べるのも不健康、食べないのも不健康という状態になるわけです。
そういう人でも最近はサプリメントという便利なものもあるので、お金さえかければなんとかなりますが。
ただ、食に関して語るとき、もう変えようのない食生活というものがあるという、身も蓋もない話も常に頭の片隅に置いておかなくてはいけません。安易に理想を押し付けないように、自分自身をへの戒めとして書き留めておきます。
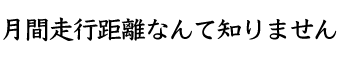

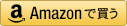








コメント