
マラソン人口が爆発的に増える段階はすでに終わり、マラソン大会はいまだに新しい大会が筍のように次々と生まれている。おそらくすでに需要と供給のバランスは逆転している。人を集めきれないマラソン大会が増えている。
大会運営側もそのことを意識しているのか、すでに人気の大会でも「もっとうまく運営しなくてはいけない」という危機感を持って大会運営をしているように感じている。
スポンサーリンク
新しく大会を興そうという人たちも、ただ大会を開けば人が集まるわけじゃないことをよく理解している。だからマラソン大会の運営に様々な工夫をしている。
その中でも地方の大会の評価の高さがずば抜けている。
2015年のRUNNETランキングでを見てみよう。
1位 第7回徳島・海陽究極の清流 海部川風流マラソン(徳島県)
2位 第10回隠岐の島ウルトラマラソン(島根県)
3位 第53回愛媛マラソン(愛媛県)
4位 第119回 ボストンマラソン(海外)
5位 第5回 北オホーツク100kmマラソン(北海道)
6位 さが桜マラソン2015
6位 第6回 安芸太田しわいマラソン2015(広島県)
残りの順位はここを参照してほしい。
ボストンマラソンは別としてずらっと地方のマラソン大会が並んでいるのがわかるだろう。これはただの偶然だろうか?わたしはこれを必然と考えている。地方のマラソンが評価されるのは運営者の努力を感じているからだ。
例えば愛媛マラソンや今回出場した下関海響マラソンは主催者の顔が見える大会だ。両方とも県知事も市長も走っている。下関海響マラソンにいたっては前下関市長の参議院議員も出場している。
こんな大会がほかにあるだろうか。自治体が一体になって本気で人を集めるためにトップから、いやトップ以上が全力で力を注いでいる。うまくいくに決まっている。
そういう大会は本気で参加者のことを考えている。下関海響マラソンは前日受付をやめて参加に必要な物を郵送に切り替えた。地方のマラソン大会において前日受付は前泊者を増やすために必須とも言える手法だ。
ところが下関海響マラソンはそれよりも参加者の利便性を再優先して前日受付をやめたのだ。経済効果を考えるとかなりのマイナスになる。でも、そのことによって大会に出たいという人は確実に増えている。
事実、下関海響マラソンの今年のエントリーは史上最速で定員に達している。愛媛マラソンは前日受付をやめていないが、参加者に対するサービスはしっかりしている。地元の人が「当たらなすぎるにもほどがある」というほどの人気大会になっている。
交通の便が悪いとかそういうことはまったく言い訳にならない。定員割れする大会はそれだけのものしか提示できていない結果なのだ。主催者の顔が見えない。参加者の一人ひとりと向き合っていない。
そういう大会はこれから継続していくのは厳しくなる。
ただ走るだけの大会を求めている人は少なくなっている。プラス何らかの走る理由がそこになければ誰もエントリーをしなくなるだろう。
そしてその「プラス何らか」を演出する力は圧倒的に地方のマラソンのほうが強い。その理由をきちんと把握しなければこれまで黙っていても参加者枠が埋まっていた大会もこれからは苦労することになるだろう。
逆に言えば地方マラソンはやり方次第でまだいくらでも参加者を集めることができる。
旅好きのわたしにとっては走りたいと思える大会はひとつでも増えてほしい。だから地方のマラソン大会には諦めずにこれからくる未来をしっかり描いてほしいと強く願っている。
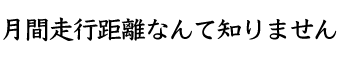








コメント