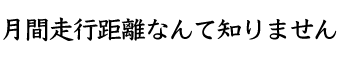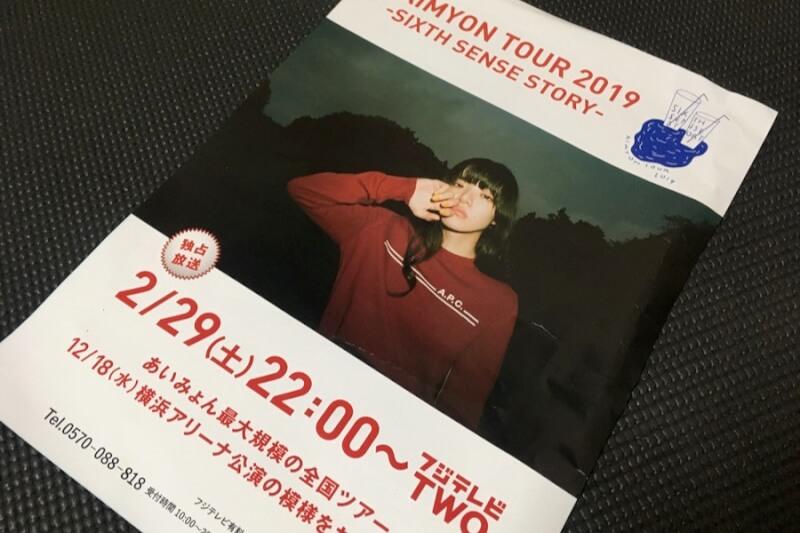
20年ぶりくらいに、音楽のライブというものに行ってきました。代々木体育館で開催されたあいみょんのライブツアー。いま話題のアーティストでチケットも取りにくいのですが、わたしがあいみょんの音楽を聴いていると知ってる友人がチケットを取ってくれました。
ライブ終わりにその友人に「どうだった?」と聞かれたわたしの答えは「嫉妬する」でした。嫉妬するし腹も立っていました。圧倒的すぎる才能とその存在感。わたしがその才能を楽しむ側にいるという苛立ち。彼女はステージに立ち自分を表現し、わたしはそれを1万人以上のお客さんと共に聴く側にいる。
わたしは自分のことを特別な存在だとは思ったことはありません。でも、曲がりなりにも表現者の1人です。自分の想いを文章という形で表現しています。自分のことをアーティストだとは思ったことはありませんが、心のどこかで引っかかるものがあったのかもしれません。
もともとあいみょんに興味を持ったのも、その表現力に打ちのめされたからです。「君はロックを聴かない」で彼女を知り、「満月の夜なら」の歌詞を聞いたときに絶望的な感情になりました。こんな表現の仕方があったことに、そして言葉を自由自在に使いこなす彼女に。
「ピンクの頬が杏色に照らされて」
そんな言葉の組み合わせは、わたしのどの引き出しを開けても見つかりません。そのとき、わたしは表現者であることをやめようかとも思いました。きっと2018年のあのときにライブに行っていたら、実際にそうしていたかもしれません。
それから新曲が出るたびに絶望感が続きました。ここ最近の数曲はタイアップが多くて、メッセージ性が強いからか分かりやすい表現を選んでいる気がしますが、それでもこれをチョイスするのかと、その言葉の組み合わせを見つけられない自分の小ささだけが浮き彫りになります。
なぜ、あいみょんに対してこんなにも対抗意識を持つのか自分でも不思議なのですが、もし人生にライバルがいるなら、おこがましくも彼女が自分にとってのライバルだと思っています。ライブに行って、その意識はより強いものになりました。
彼女は切り取った瞬間を情景として表現している。それがわたしなりの気づきです。刹那的であり儚さも感じます。彼女はあまり未来について歌いません。今その瞬間に起きたことを、歌詞として表現しているようにわたしは感じます。次の瞬間には消えてしまう何かを。
それが独特のリズムと無限に広がる歌声で、彼女だけの世界を作り上げています。リズムや声というものには嫉妬することはなく、ただ感心するばかりです。それらがうまく重なり合ったとき、わたしは何度となくその世界に引き込まれ、熱狂する一歩手前のところに立っていました。
こういうときに熱狂できる人間ならどんなに人生が楽しいだろうと思うことがあります。わたしは、いつも熱狂の輪の中に入ることができず、それは性格なのだと思っていました。でも、ライブに行ってわかりました。わたしは熱狂をする側ではなく、熱狂を生み出す側の人間なのだと。
実際に熱狂を生み出せるかどうかはわかりません。少なくともクリエイティブな側の人間なのは間違いありません。クリエイティブであることが優れているというわけではなく、どちら側の人間かという話です。世の中はクリエイティブな人間と、そこから生み出されたものを楽しむ人間に分かれます。
クリエイターと消費者はお互いの存在に依存します。クリエイティブな人は、それを消費する人がいるから才能を認められ、表現することができます。創造物を消費する人は、クリエイティブな人がいるからその創造物を楽しめます。
お互いに補完しあう存在だから上手くいきます。
わたしはクリエイティブでもなく、消費者でもないというスタンスに自分を立たせてきました。無意識の部分でも、意識的な部分でも。でも、悔しいと思うということは、やっぱりクリエイティブでありたいのでしょう。評価されるかどうかは別として、消費されるものを作り出したい。
消費という言葉のチョイスがすでに表現者としての限界を示しています。この言葉を、この感情をあいみょんならどう表現するのでしょう。考えただけでも苛立ちが大きくなります。
もしかしたらこの感覚を劣等感と呼ぶのでしょうか。44年生きてきて初めて味合う感覚なので、心の奥がざわついて穏やかでありません。最高の1日になりました。たぶん、わたしはこの日のことを忘れることはないでしょう。あいみょんの歌を聴くたびにこれからも胸がざわつくのでしょう。
きっと、数年後にあいみょんと対等に会話を交わせる表現者になって、そこで「実は代々木に観に行ったんですよ」と言えるようになるまでは、この感情が消えることはないのでしょう。20歳ほど年齢が違いますが、同じ時代に背中を触れたいと思える人がいたことをありがたく思います。
この想いを妄想に終わらせるかどうかはわたし次第。もちろん、妄想で終わらせるつもりはありません。圧倒的な努力で、その背中に爪先くらいは届かせてみせます。