
24時間マラソンの疲労もだいぶ抜けてきましたので、ハルカススカイランに向けての練習を再開しました。1kmタイムトライアルの後にジャンプ練習。
タイムトライアルは前回の3分29秒に対して今回は3分33秒。イメージではもう少し走れているつもりでしたが、タイムは付いてこず。ただ筋力が多少落ちていることを考えれば許容範囲内です。
筋トレでつけた筋肉というのは使っていないと当然落ちてきます。ナチュラルな筋肉ではありませんので使い続けることが重要なのですが、今回はいわて奥州きらめきマラソンもあり1ヶ月もジャンプ練習をしていませんでした。
そう考えると許容範囲内どころか、むしろ今後への期待が高まります。この1ヶ月で新しく取り組んだことが、思った以上にいい方向に向いている。そんな気がしています(気のせいかもしれませんが)。

スポーツの世界では「1日休むと取り戻すのに3日かかる」というような言葉があります。この言葉にとらわれて上手に休むことのできないランナーがかなりの数いるように感じています。
マラソンはいかに上手に休むかが重要なスポーツです。
できるだけ短い期間でコンディションを回復させ、高い強度の練習を積み重ねていく。高強度の練習をして回復に3日かかるのと、2日かかるのとでは1年間にできる高強度の練習回数が違ってきます。
片方は4日に1回しか高強度の練習ができず、もう一方は3日に1回です。1年間に出来る強度の高い練習の回数は前者で73回、後者は91回。どちらが成長するかは言うまでもありません。

ただ、ここで重要なのは練習の回数のことではなく、回復時間がないと高強度の練習ができないということです。
ところが、「1日休むと取り戻すのに3日かかる」の発想になると、休む暇がありません。毎日高強度の練習をしているつもりが、実はそれほど強度の高くない練習をダラダラ続けているだけだったということになりかねません。
生理学的に考えても、強度の高い練習をしたあとにはある程度の回復期は必要です。世界中どこを探しても、高強度の練習を毎日続けているトップアスリートはいません。
毎週のようにフルマラソンを走る川内優輝さんでも、回復をとても重視しています。

それなのに、市民ランナーになるとなぜか毎日ハードな練習をしようとします。特にマラソンを始めたばかりで、走れば走るほどタイムが伸びる時期にはがむしゃらに走り込みます。
そしてケガをするのがお決まりの路線。そこで「シューズが悪い」と裸足になるマイノリティもいますが、シューズが悪いのではなく悪いのは回復を考えずに走り続けた自分自身です。
「いや、でも裸足になったら治ったし」そういうかもしれませんが、まず間違いなく練習量はシューズのころよりも減っています。もちろん裸足の効果もありますが、裸足だって追い込む練習を毎日していたら足は壊れます。
それはまた別の話ですので、今日はあまり引っ張りません。

問題は「1日休むと取り戻すのに3日かかる」なんです。なぜそのような考え方が定着しているのか。実はこの言葉、きちんと元になったものがあります。
1日練習しなければ自分に分かる
2日練習しなければ批評家に分かる
3日練習しなければ聴衆に分かる
フランスのピアニスト、アルフレッド・コルトーの言葉です。この人にはもうひとつ有名な言葉があります。
50代は40代の2倍
60代は40代の3倍
70代は40代の4倍の練習量が必要になる
練習の鬼ですよね。でも、彼は四六時中練習をしろとは言いません。「1日5時間以内」の練習時間を推奨しています。ようは1日10時間やって次の日に休むのではなく、短い時間でも毎日続けることが大事だと。

ランニングでも基本的には同じだとわたしは思います。2日に1回10km走るよりも毎日5km走ったほうがいい。ただし、ピアノとは違い筋肉を使いますので、ランニングは毎日してもポイント練習は3〜4日に1回が理想です。
この毎日続けるランニングと強度の高い練習を一緒に考えるから話が複雑になります。「1日休むと取り戻すのに3日かかる」からジョグのような軽いランニングは毎日続ける必要があります。
それとは別に強度の高い練習は、筋肉を回復させなくてはいけませんので毎日はしません。そこはしっかり2日以上休まなくてはいけません。こちらは「1日練習をすると体が戻るのに2日かかる」というわけです。
テクニックとフィジカルの違いと言えば分かりやすいかもしれません。テクニックは継続が重要ですが、フィジカルは回復が重要です。

練習にメリハリをつけることができるかどうか。ケガをせずに、高いレベルを保ち続けるにはそこが鍵になってきます。若いうちは毎日フルパワーでがんばれたかもしれませんが、30代後半以降になるとそうもいきません。
がむしゃらにやれば成長できるというのは間違った思い込みです。むしろ頑張らずに無理のない範囲内で毎日継続すること。そしてそれを習慣化することが大切です。
言うは易く行うは難しですが。
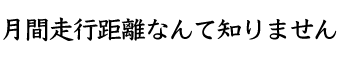

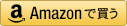








コメント