
マラソン大会シーズンということもあって、FacebookやTwitterのタイムラインには、自己ベスト更新やら思ったように走れなかったやら、いろいろとにぎやかな状態になっています。
最近はFacebookの投稿をする人が減っているので、久しぶりの顔を見れたりでいいもんだと思いながら、やっぱりみんなタイムを気にするんだなと再確認しました。
わたしはタイムを追うのをやめて1年くらいでしょうか。速く走れるようになりたいという思いはありますが、自己ベスト更新やシーズンベストなどにはまったく興味がなく、国宝松江城マラソンも後になって愛媛マラソンと同じようなタイムだと気づいたくらいです。
速くなりたいというのは正確ではなく、上手に体と対話ができるようになりたいというのが正しい表現かもしれません。結果的に速くなれるので同じことのような気がしますが。

タイムを追わないのは、走りが苦しくなるのが嫌だというのもありますが、タイムが最優先されると自分の走りを見失う可能性があるためです。自己ベスト更新を狙う場合、完走目標タイムからペースを逆算することになります。
サブ3なら4分15秒/km。サブ3.5なら5分/kmくらいがひとつの目安になりますが、本当はペースが先にあって、その先に完走予想タイムがあるはずです。自分が無理なく走れるペースを考えて、そこから積み立てていくのが理想です。
ところがサブ3を目標にするなら、「4分15秒/kmで走らなきゃ」と自分を追い込みます。しかも失速するかもしれないから、前半は4分10秒くらいで……なんてことを考えます。
そもそも4分10秒/kmで走りきれるなら、サブ3なんてとっくに達成しています。完走時間を先に決めるからオーバーペースになって後半失速。PB更新ができなくなるわけです。

それだけではありません。レースペースというのは、その日の気温や湿度、天気などの要素も影響します。自分自身の仕上がり具合も考えなくてはいけません。コースの渋滞具合も無視できません。
要するに、走ってみないとその日のペースは決まりません。わたしはタイムを追うのを止めてから、最初の14kmでペースを掴んでそれを体になじませるようにしています。これをするようにしてから後半に失速したことは1度もありません。
問題はペースが定まるまでは完走予想タイムが分からないという点にありますが、そもそも走る前にタイム設定をすることが間違っているというのがわたしの考え方ですから、完走予想タイムなんて分からなくてもいいんです。
ゴールで友人が処刑されそうになっているのでなければ。

自分で決めたペースを淡々と積み重ねていくだけ。他の人がどうなのかは知りませんが、これこそがマラソンだなとわたしは感じています。もちろんペースを決めるのはそれまでの練習があってのことです。
希望するペースで走れるようになるには、どんな練習をすべきかを考えます。そして、その練習をするためにはどれだけのリカバリー期間が必要になるかを考えて、練習スケジュールを組み立てます。
わたしにとってはそこまで含めてマラソンで、その楽しさにようやく気づき始めたところです。
ワークマンの980円のランニングシューズでサブ3.5を達成したのは、シューズのおかげでもなければ自分に才能があるからでもなく、きちんと練習を積んで、正しいペース設定ができたから。

すべてがうまく噛み合ったことに気持ちよさはありますが、このタイムをすごいとは思いません。そもそも3時間半で走りたいという希望もありませんでしたし、最終的にペースを決めたのはスタートしてからです。
レースを走っていると「そんなことをしてまでタイムを出したいの?」と思うようなことをするランナーにたくさん出会います。強引な追い抜きやコース外走行、不正なタイム申告など。
そういうことをして出したタイムってどれくらい価値があるのでしょう。マラソンで大事なのは速いタイムで走ることではなく、今日の自分のベストを尽くすことであり、弱い自分に負けないことだと、わたしは思っています。
過去の自分と比較することに大した意味はありません。昨日の自分と今日の自分は同じわけではないわけですから。

でも、それでは自分がやりきったかどうかが分からないから、過去の記録を引き合いに出して「頑張れた」「失敗だった」なんてことになるわけです。でも本当は分かっているはずです。
過去の記録と比べなくても自分がベストを尽くせたかどうかなんて。
きちんと練習を積み重ねることができたのか。現状の自分を冷静に判断してペースを決めて走ることができたのか。最後まで諦めない走りができたのか。
全部自分が1番わかっているはずです。
別にタイムを追うのを止めたほうがいいなんてことは言いませんが、速ければ偉いわけでもありませんし、大事なのは記録を出すまでの過程であって、結果はわかりやすい評価のひとつに過ぎません。
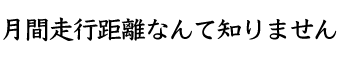

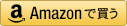








コメント