
「ランニングは肩甲骨が重要」って言われたけど、いまいちピンときてない人いますよね。
走る時には腕振りが大切だと習った人もいると思いますが、わたしを含め一部の人は「大事なのは腕振りじゃなくて、肩甲骨を走りに連動させること」って主張するから余計に頭の中が「?」になってますよね。
そんな人のために、肩甲骨が走りにどんな影響を与えるのか、ちょっとだけ感じてもらう方法に気づきました。
肩甲骨の動きは骨盤の動きにつながる

以前「「run to adjust」走ることで体が整うという可能性」で、両手を体の後ろで組んで走ると、肩甲骨と走りの連動が分かりやすくなると書きましたがその応用です。
まず後ろで手を組んで、ジョグくらいのゆっくりなスピードで走ってください。
ある程度安定して走れるようになったら、その状態で腕に軽く力を入れて、肩甲骨をグッと内側に寄せてください。手を組まなくても肩甲骨を寄せられる人は組まなくても大丈夫です。
肩甲骨を寄せていくと、両足の幅が狭くなって右足と左足が擦れたりぶつかったりするのを感じられたら正解。
実際には足の幅が狭くなっているのではなく、骨盤が閉じることによって両足の距離が近づいて足同士が擦れます。
肩甲骨を閉じると骨盤が閉じ、肩甲骨を開くと骨盤が開く。これが人間の体の仕組みであり、走りと肩甲骨の関係になります。
肩甲骨の動きは骨盤の動きに勝手に連動するのが、体の仕組み。
この感覚をつかむと、右側の肩甲骨を後ろに引くと骨盤の左が前に出ることをはっきりと分かるようになるはずです。
間違った腕振りが故障を招くという推論

ここですでに「?」になっている人いると思います。
感覚がまだ鈍いだけか、肩甲骨と骨盤が上手に連動していないかのどちらかですが、どちらにしてもランニングにおいて「腕振りがマイナスになっている人」だと思います。
肩甲骨と骨盤を連動させずに腕振りをするとどうなるか。
速く走れないだけならまだいいのですが、おそらくこれは腰痛や膝痛につながります。医学的な知識がないのであくまでも「推論」であることを理解して読んでもらいたいのですが、ランニングによる腰痛や膝痛は腕振りにも原因があるような気がします。
上手に肩甲骨と骨盤を連動させることができたら、体の背面の筋肉には不要な負荷がかかりません。
ところが連動しない間違った腕振りによって、人間の本来持つ体の動きを阻害することになります。そして人間の体の仕組みに反する動きを何度も繰り返すことで腰や膝の故障につながる。
もう一度書いておきますが、あくまでも推論です。
速く走るためのフォームがナチュラルなわけではない

速く走るためのランニングフォームというのはいろいろな専門家が研究し、そしてある一定の結果を出しています。でもそのフォームはどこか体に無理をさせている、そんな気がしています。
無理に体の中で筋肉の反発を起こさせて、前進するエネルギーを生み出し、人間が出せる限界以上のスピードで走り続けるために最適なフォームが「正しいフォーム」とされている。
結果を出すという意味では確かにそれが正しいのかもしれませんが、ランナーの99%以上は体を壊さずに走ることが大事であって、むしろ健康になるために走っているはずです。
なのに体に間違ったフォームで体に負荷をかけることでケガをしてしまう。
「ランニングにケガはつきもの」みたいなことがあたり前に言われているのがいまのランニングの世界ですが、その認識はそろそろ変えたほうがいいんじゃないかと、わたしは思います。
ランニングでケガをするのは、体に無理な動きをさせているから。きちんと人間が本来持つ動きで走れば、「使いすぎ」以外でランニングでケガをすることはほとんどないはずです。
肩甲骨と骨盤を連動させる感覚をつかむ

体を連動させる感覚をつかむトレーニングは、本当は走り始める前にやるべきことなんだと思います。
でもそんなこと教える人はほとんどいないから、みんないきなり自己流でランニングを始めてしまう。でもとりあえず走れるからそのまま走り続けてケガをする。
ちゃんとランニングスクールで習っても「体の連動の感覚」なんていうコーチはどれだけいるのでしょう。
「体の連動の感覚」なんてランニングスクールで教えてたら、その日のトレーニングはヘタすると一歩も走らないで終わってしまいます。たぶん習う側も納得しないでしょうね。
でも「体の連動の感覚」を身につけずに走るということは、酸素ボンベの使い方を習わずにスキューバダイビングするようなもの。ラケットの使い方を教わらずにテニスをしたり、クラブの握り方を知らずにゴルフをするようなもの。
だからまずは肩甲骨と骨盤の連動を感じる練習から初めてみませんか?
両手を体の後ろで組んで、肩甲骨を寄せたり開いたりして、足の幅が変わる感覚をつかんでみてください。すぐには理解できないかもしれませんが、何度もやっているとわかってきます。
一度その感覚をつかめばあとは応用です。肩甲骨を引いたときどうなるか、肩甲骨を上げたときは?反対に下げたときは?自分で連動を感じる練習をしてください。
その中で自分にとって最適な肩甲骨の位置と動きを見つけてください。
あとはその連動を走りにつなげるのですが、それはまたいずれということで。
スポンサーリンク
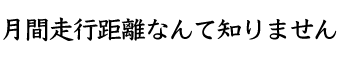








コメント