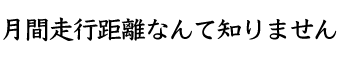猛特訓をして自分の限界を超えていく。スポ根世代にはその考え方が根強く染み付いていて、マラソン練習でもオーバートレーニングになりがちです。10kmのジョグでいいはずが、15kmのペース走になってしまった経験のある人も多いはず。
ジョグではなくポイント練習の日に、オーバートレーニングになる人もいます。私がそのタイプで、ポイント練習は超回復理論に基づくトレーニング方法なので、本来であれば72時間後には疲労が完全に抜けていて、次のポイント練習をベストコンディションで実施する必要があります。
でもオーバートレーニングになっているので、中2日で回復しきらず疲労が溜まった状態で次のポイント練習をしてしまう。その積み重ねで体が悲鳴をあげてケガをする。シリアスランナーがケガをするときは大抵このループに入っているのではないかと私は考えています。
中2日で回復していない場合、ポイント練習の日をずらす必要があるのですが、そもそも中2日で回復できていない時点で問題があります。中2日で回復できない理由として考えられるのが、ジョグのペースが速すぎるかポイント練習の負荷が高すぎるかのどちらか、もしくは両方。
ここで大事なのは確実に中2日で回復させるということ。でも、実際にトレーニングをしているとどうしてもポイント練習の負荷を上げすぎてしまいます。ポイント練習はハイテンションになりやすく、「もっといける」という思考になりがちなので。
スポ根世代は「もっといける」のに負荷を軽くすることで、トレーニング効果が得られないのではないかと不安になる。だから90%の出力でいいのに100%を出してしまう。8本でいいのに10本やってしまう。そうなるとやりきった達成感は得られますが、トレーニングとしては失敗です。
まずは「がんばったら、それに応じた見返りがある」という思考を捨てなければいけません。72時間後に完全に回復するのがどれくらいの負荷なのか自分なりに試行錯誤し、さらに成長に合わせてアジャストしていく。ここがマラソントレーニングの難しいところです。
だから、トップアスリートでもコーチを付けるわけです。コーチの役割はいろいろありますが、オーバートレーニングを防ぐというのも大きな役割のひとつです。コーチがいない一般のランナーは「走った距離は裏切らない」なんて言葉に惑わされるわけです。
実際に走った距離は裏切りませんが、どう積み重ねたかはとても重要になります。オーバートレーニングで積み重ねた距離は確実に私たちランナーを裏切ります。あくまでも中2日で回復できる範囲での距離であることが前提となります。
そういう意味ではフルマラソンそのものが、私たちランナーにとって厄介な存在になります。一般的にタイム重視でレースを走った場合、回復するのに1マイルにつき1日かかるとされています。フルマラソンは42kmで回復するのに約26日かかります。
これは26日間、成長が止まることを意味します。私がこれから1年間ハーフマラソンを主軸にするというのは、フルマラソンを走ることで成長が止まるのを防ぐためです。それでも何レースか入れていますが、台北マラソンもしくはいわて盛岡シティマラソン以外は全力で走らないつもりだから。
2025年の愛媛マラソンに焦点を合わせているので、これはもう仕方ないことです。フルマラソンを走って体の回復を待つ時間を作るよりは、継続してトレーニングをして自分のポテンシャルを100%引き出す。そのためにも頑張りすぎないことも2024年の課題のひとつです。